○庄原市の記念物一覧と他地域の記念物についてはこちらから
史跡一覧
天然記念物一覧
国指定
| 名称 | 地域 | 種類 |
県指定
| 名称 | 地域 | 種類 |
| 上高野山の乳下がりイチョウ | 高野 | 植物 |
| 上湯川の八幡神社社叢 | 高野 | 植物 |
| 南の八幡神社社叢 | 高野 | 植物 |
| 円正寺のシダレザクラ | 高野 | 植物 |
| 金屋子神社のシナノキ | 高野 | 植物 |
市指定
| 名称 | 地域 | 種類 |
| 長妻家りんご樹 | 高野 | 植物 |
| 王居峠神社社叢 | 高野 | 植物 |
| 上市大山神社のモミ | 高野 | 植物 |
| 山根荒神社のシナノキ | 高野 | 植物 |
| 多賀山神社のヒノキ | 高野 | 植物 |
| 田部家のイチイ | 高野 | 植物 |
| 奥ノ名のオオウラジロノキ | 高野 | 植物 |
| 和南原のウワミズザクラ | 高野 | 植物 |
▲上へ戻る
史跡
蔀山城跡

| 読み方 | しとみやまじょうあと |
| 指定 | 県指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | |
| 指定年月日 | 平成4年10月29日 |
| 所在地 | 庄原市高野町新市 |
| 構造形式 | 中世の山城跡 標高775m、比高220mの尾根筋にある。 遺構は東西に延びる山頂郭群を基本とし、南郭群、北東郭群などからなる。 本丸跡や段差を利用した数箇所の郭跡がある。 |
○高野町新市の盆地の束端に位置し、西流する神野瀬川に南流してきた毛無川が交わる上市集落の北東側に位置する。
○室町時代中期(15世紀)以前に遡って城主を推定する史料をもたないが、正和五年(1316年)鎌倉から首藤山内三郎兵衛尉通資が地毘庄地頭とし来、築城し越田城と称していたが、武衛繁盛を念じ士富士と改めた。戦国時代(16世紀)には、鉄の生産、流通が盛んであった備後北部から出雲南部にかけての山間地域に大領域を領有していた多賀山氏の本城であった。山陰側の尼子氏と山陽側の大内氏、続く毛利氏の両勢力が拮抗する境目領主の拠城として注目される。
▲上へ戻る
天然記念物
上高野山の乳下がりイチョウ

| 読み方 | かみたかのやまのちちさがりイチョウ |
| 指定 | 県指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和12年5月28日 |
| 所在地 | 庄原市高野町新市 |
| 構造形式 | 根回り周囲 10.10 m 目通り幹囲 9.60 m 樹高約18 m |
○本樹は県内第1位のイチョウの巨樹で、多数の乳柱(乳房状突起)が垂れ下がる雌樹である。乳柱は局部的な栄養過剰によって生ずるといわれ、実がならない老木に多く見られるが、本樹のような実のなる雌株にできることもある。
○天平元年(729年)、建御雷神(たけみかづちのかみ)をこの地に勧請したとき、神木として植えられたと伝えられる。
▲上へ戻る
上湯川の八幡神社社叢

| 読み方 | かみゆかわのはちまんじんじゃしゃそう |
| 指定 | 県指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和34年10月30日 |
| 所在地 | 庄原市高野町上湯川 |
| 構造形式 | 胸高幹囲2m以上の樹木が45本 モミ(胸高幹囲:6.0 m、樹高:約36 m)、スギ(胸高幹囲:7.0 m、樹高:33m)は県内有数の巨樹。 |
○スギを中心とした針葉樹と落葉広葉樹からなる高野地方の代表的な社叢である。一説では、天正年間(1572~1591)に土居城主・湯川兵部亟通長が現地に社殿を移し社領を若干寄進したという。
○本社叢は旧県道を背にする平坦地に展開し、史跡は3反と比較的狭いが、スギを主として若干のモミ・カヤなどの針葉樹と、エノキ・ヤマモミジ・ミズキなどの落葉広葉樹からなる当地方の代表的な社叢である。
▲上へ戻る
南の八幡神社社叢

| 読み方 | みなみのはちまんじんじゃしゃそう |
| 指定 | 県指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和34年10月30日 |
| 所在地 | 庄原市高野町南 |
| 構造形式 |
○社叢は、神殿周辺部と、参道部の二部からなる。社殿付近には、幹囲2m以上のスギ、モミ、クロマツ、ヤマモミジなど約20本がほぼ一団をなす。参道にも同様な幹囲のスギ、モミ、アベマキなどが並木をなしており、幹囲2m以上の大樹だけでも50本以上の多きに達する。わけてもモミは胸高幹囲5.02 m、アベマキは同4.05 mに達する県内有数の巨樹である。
○元享元年(1321年)蔀山城の城主山内首藤通資が鶴岡八幡宮を当地に祭るにあたり植樹したと伝えられる。
▲上へ戻る
円正寺のシダレザクラ

| 読み方 | えんしょうじのシダレザクラ |
| 指定 | 県指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和34年10月30日 |
| 所在地 | 庄原市高野町新市 |
| 構造形式 | シダレザクラ 2本(東株・西株) 円正寺境内鐘楼門の左右にある2本のシダレザクラ。ヒガンザクラの一変種。
|
○シダレザクラは特異な樹形のため古来各所の社寺庭園などに栽培され銘木となっているものが多いが胸高幹囲3mを越すものは少ない。
○本樹2株は県内有数の巨樹としてだけでなく枝上が四方に展開してあたり一面を覆い、銘木として見るべきものがある。住持乗覚法師(明暦3年生(1657年)圓正寺11代)が中年代に鐘楼門建立の際に植栽したと伝えられる。
▲上へ戻る
金屋子神社のシナノキ

| 読み方 | かなやごじんじゃのシナノキ |
| 指定 | 県指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和34年10月30日 |
| 所在地 | 庄原市高野町新市 |
| 構造形式 | 根元の東側に大きな切株があり、これに接して本樹がある。 主幹の根周り975cm、胸高幹囲500cmで地上約3mで、折損している。代わる大支幹が主幹の空洞を貫いて地上1.5mのところで主幹と分かれる。樹高約10mに達して約14m2の地積をおおい崩茅性の旺盛なことを示している。 この状態は、主幹が東側の切株から西に向って3代目の移動を想起させる。 |
○シナノキは日本ならびに中国に自生する落葉高木であるが、特に東北地方と北海道に多い。その樹皮を布や綱の材料として利用してきたため、巨樹はきわめて少ない。本樹は神社境内のために残したと思われる。
○高野地方ではカネルの木と呼び、繊維は、牛の子ぐるままんがの元綱など湿気の多いところに使用されていた。
○神社は、文政7年甲申(1824)の年に遷宮式を行ったと古文書にあるが、シナノキはまだ古い年代と思われる。
▲上へ戻る
長妻家りんご樹

| 読み方 | ながつまけりんごじゅ |
| 指定 | 市指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 平成9年1月9日 |
| 所在地 | 庄原市高野町下門田 |
| 構造形式 | 昭和10年植栽のりんごの樹 (当初は3本の樹木を指定していたが、豪雪等により枯死した1本が平成16年12月に解除された。) |
○特産品である「高野りんご」を築き上げた草分けの樹である。
○高野でのリンゴの栽培歴は古く、大正12年島根県の桜井氏が和南原篠原開拓時に、リンゴを含む数種類の果樹を植栽したのが始まりと伝えられている。
○昭和10年に下門田只野原開墾地に庄原実業高校下高野山分農場が置かれ、数種の農作物が試作された。その内果樹(リンゴ、桃、梨、栗)は93a植栽されたが、そのとき植栽されたリンゴの樹が本件の指定樹である。
○栽培果樹のために人為的に仕立てられており、古来仕立ての自然開芯形3本仕立てにより、主幹・亜主枝・徒長枝によって樹形が形成されている。また、亜主枝上部には改良された品種が接木されている。
▲上へ戻る
王居峠神社社叢

| 読み方 | おいだわじんじゃしゃそう |
| 指定 | 市指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和55年8月23日 |
| 所在地 | 庄原市高野町上湯川 |
| 構造形式 | スギ9本 モミ1本 コナラ1本 ナラガシワ1本 ホオノキ1本 ミズキ1本 (平成16年の調査による) |
○本社叢林は、高木層は上記のような樹種で構成され、低木層は常緑樹林に多く生育するアオキと、落葉樹林で多く見られるエゾユズリハが共存しており、特異な植生を形成している。
○台風の影響によりナラガシワが倒れ、現在は失われている。
▲上へ戻る
上市大山神社のモミ

| 読み方 | かみいちだいせんじんじゃのモミ |
| 指定 | 市指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和55年8月23日 |
| 所在地 | 庄原市高野町新市 |
| 構造形式 | モミ(マツ科) 1. 境内: 樹高約30 m、樹高囲 4.33 m 2. 境内下法面:樹高約30 m、樹高囲 4.30 m |
○モミは本州(秋田県・岩手県以南)・四国・九州(屋久島まで)の山地に自生し、比較的低所に多い。樹高さ35~40mになる常緑の高木で、樹皮は灰色~暗灰色で、鱗片状にはがれる。
○上市大山神社(別名蔀山神社)は、古くは越八馬頭身社(はうやまずみしゃ)として称え、蔀山の山頂にあったが、元応元(1319)年、蔀山城主首藤通資が現在の社地に移し、地毘荘内の牛馬の総守護神と定めた。近世はもっぱら大山権現社と称えられたが、明治4年に蔀山神社と改称された。
○本件のモミ2本は境内およびその近辺に位置し、ともに神木として保護されてきたと考えられる。
▲上へ戻る
山根荒神社のシナノキ

| 読み方 | やまねこうじんじゃのシナノキ |
| 指定 | 市指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和55年8月23日 |
| 所在地 | 庄原市高野町新市 |
| 構造形式 | シナノキ(シナノキ科) 樹高約25 m 樹高囲約4 m |
○シナノキは北海道・本州・九州の山地に自生する高さ8~10mほどの落葉高木であり、大きいものは30mにもなるという。地元では「カネリ」と呼び、用材は障子の組子などに使用した他、樹皮からは繊維を採り、縄として利用した。
○本樹はシナノキとしては県内第3位の巨樹で、山根荒神社の傍にあり神木として保存されている。主幹が南西へ8度傾いているものの、着生植物はなく、樹勢は良好である。
▲上へ戻る
多賀山神社のヒノキ

| 読み方 | たがやまじんじゃのヒノキ |
| 指定 | 市指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和55年8月23日 |
| 所在地 | 庄原市高野町下門田 |
| 構造形式 | ヒノキ(ヒノキ科) 樹高約38 m 胸高幹囲約5.03 m |
○ヒノキは本州(福島県以南)・四国・九州(屋久島まで)に分布し、山地に自生する。樹皮は灰褐色~赤褐色で、縦裂し薄くて長く裂片に剥がれる。花は4月に開花し、雌雄同株である。常緑高木で、大きいものは高さ約30mになる。
○多賀山神社は、永禄3(1560)年、士富山城主の多賀山内首藤伯耆守通続が家臣坂本城主白根加賀守に命じて社殿を造営せしめ、坂本大将軍社と称して崇敬したことに始まる。大正4年に下高地区大字名の氏神4社を合祀し多賀山神社と改称、神威いよいよ高く仰ぎて崇敬を集め今日に到る。
○本樹は、多賀山神社の御神木として保護されてきたと考えられ、県内有数のヒノキの巨樹として貴重である。
▲上へ戻る
田部家のイチイ

| 読み方 | たなべけのイチイ |
| 指定 | 市指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 昭和55年8月23日 |
| 所在地 | 庄原市高野町上里原 |
| 構造形式 | 樹高約5 m 胸高幹囲約3.0 m |
○イチイは北海道・本州・四国・九州、千島・樺太・朝鮮・中国(東北)・シベリア東部に分布する常緑の高木で、高さ15~20mにも達するが、ときに低木状で這うものがある。花は3~4月に開花し、その年の10月ごろに果実が成熟する。
○本樹は雌株のイチイで県内6位の巨樹であり、また個人宅の庭にあるため手入れも行き届いており、銘木である。
▲上へ戻る
奥ノ名のオオウラジロノキ
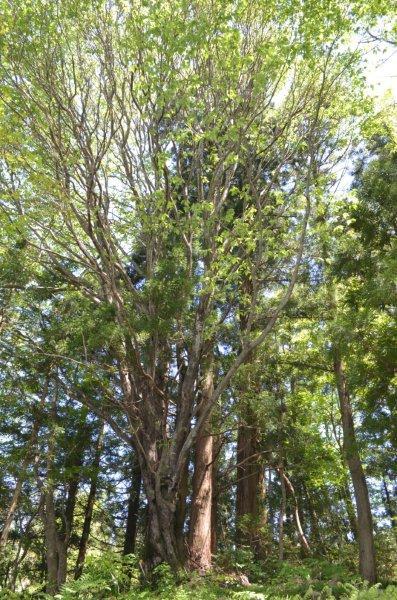
| 読み方 | おくのみょうのオオウラジロノキ |
| 指定 | 市指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 平成21年3月26日 |
| 所在地 | 庄原市高野町和南原 |
| 構造形式 | オオウラジロノキ(バラ科) 根回周囲 3.0 m 胸高幹囲 2.8 m 樹高約16 m 地上約2.4 mの位置で分岐している。 |
○オオウラジロノキは、本州・四国・九州に分布しており、県内では中国山地に稀に自生する。地元ではヤマナシと呼び、昔は木馬の材料や生活に密着した器具材等に用いられ、果実は水浸後、カマスに入れ庭木の上で発酵させ食べていた。
○そのような有用木であるため、伐採を受ける機会が多かったにも関わらず、本樹が今日まで残されたのは、所有者によって意識的に保護されてきたということであり、そのような歴史的経緯を勘案しても注目すべきであり貴重である。
▲上へ戻る
和南原のウワミズザクラ

| 読み方 | わなんばらのウワミズザクラ |
| 指定 | 市指定 |
| 種別 | 記念物 |
| 種類 | 植物 |
| 指定年月日 | 平成21年3月26日 |
| 所在地 | 庄原市高野町和南原 |
| 構造形式 | ウワミズザクラ(バラ科) 根回周囲 1.9 m 胸高幹囲 1.7 m 樹高約15 m |
○ウワミズザクラは、北海道(石狩平野以南)・本州・四国・九州(熊本県南部まで)に分布する。葉の展開後、新枝の先に白い小さな総状花序を多数付け、果実は秋に赤色から黒色に熟す。地元ではミズメザクラまたはネズミザクラと呼んでいる。ヤマザクラの代用として敷居などに利用した。
○本樹はウワミズザクラ属の樹木としては巨樹である。
▲上へ戻る








 アクセス
アクセス よくある質問
よくある質問
