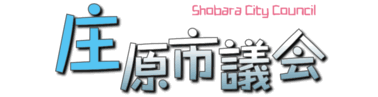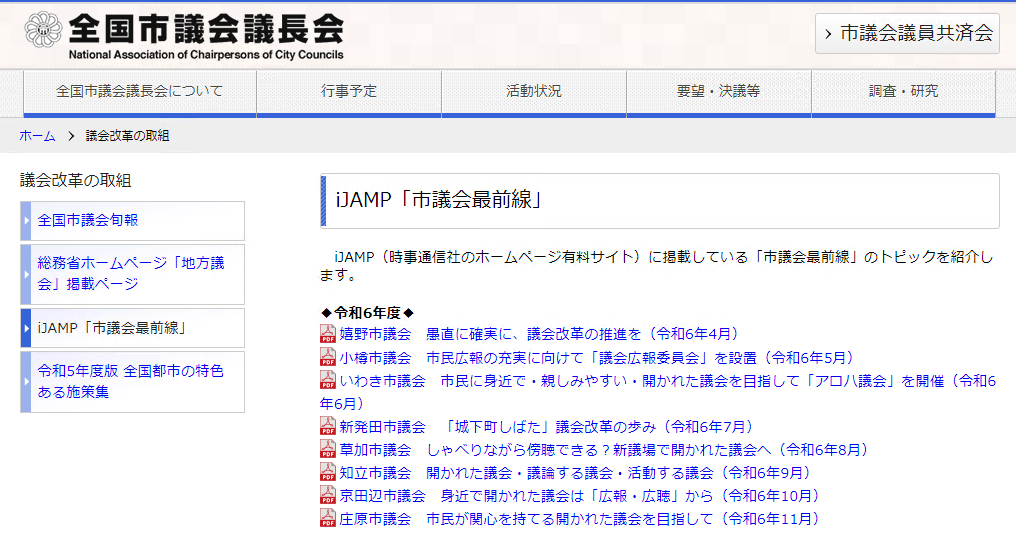トピックス
ここでは、市民のみなさんに知っていただきたい市議会に関する話題等について掲載しています。
ユーザーが約50万人いる時事通信社HPの有料サイトの情報コーナーiJAMP「市議会最前線」トピックに本市議会の取り組みが掲載されました。
庄原市議会では、庄原市議会基本条例において議員間相互において十分な議論、討論を尽くして合意形成に努め、その結果について市民に対しての説明責任を十分に果たすとともに、議員間の自由な討議を重んずる旨を定めています。
そのため、本年度は、テーマを「常任委員会における議員間討論の活性化について」とし、講師に、平成11年に、全国最年少となる27歳で徳島県川島町長に当選され、町長を2期努められた後、地方自治の探求を目的に早稲田大学大学院に入学し、首席で修了され、現在、早稲田大学マニフェスト研究所事務局長として、自治体の行政・議会双方の支援を精力的に行われている「中村 健 さん」をお招きしました。
研修会では、混同しがちな「議論」・「討論」・「討議」の定義から丁寧にお話しいただき、議員間では、主張の正当性を争ったり、説得するのではなく、率直な意見交換をすることで、共通理解を探し出す「討議」が重要であることの説明を受けました。議員からは、自己主張に終始するのではなく、広い視野で意見交換をすることが、結果として、相互理解による共通の着地点を見出し、大きな成果につながる可能性が理解できた等の感想がありました。
庄原市議会では、「投票率の低下」や「無投票当選の増加」等、全国的に地方議会が抱える様々な課題に対応するため、令和5年度から「広報広聴活動の充実化」を目標に掲げ、市民の皆さまに市議会の活動を知っていただくための様々な取り組みを検討しています。
その中で、将来の庄原市を担う子ども達に市議会に対する理解を深めてもらうことが非常に重要であると考え、議会運営委員会を中心に、市議会について分かりやすく理解するためのツールの一つとして「庄原市議会ガイドブック」の作成に取り組みました。
主には、市内の中学生・高校生を対象と考えて作成したものですが、日ごろなかなか触れることのない市議会の概要をまとめていますので、是非ご覧ください。

庄原市議会ガイドブック(改訂中)
令和6年11月6日(水曜日)
◆庄原市議会の取り組みがiJAMP「市議会最前線」トピックに掲載されました!
ユーザーが約50万人いる時事通信社HPの有料サイトの情報コーナーiJAMP「市議会最前線」トピックに本市議会の取り組みが掲載されました。
トピック掲載市は各月ごとに、全国市議会議長会の部会(北海道・東北・北信・関東・東海・近畿・中国・四国・九州)が持ち回りで推薦した市の内容が掲載されることとなっており、令和6年11月に中国部会が該当し、本市の記事が推薦されたものです。
なお、掲載記事の内容は、全国市議会議長会のホームページからどなたでも確認することができますので、ぜひご覧ください。
なお、掲載記事の内容は、全国市議会議長会のホームページからどなたでも確認することができますので、ぜひご覧ください。
↑
こちらのURLから該当ページにアクセスできます
令和6年7月19日(金曜日)
◆令和6年度庄原市議会議員研修会を開催しました庄原市議会では、庄原市議会基本条例において議員間相互において十分な議論、討論を尽くして合意形成に努め、その結果について市民に対しての説明責任を十分に果たすとともに、議員間の自由な討議を重んずる旨を定めています。
そのため、本年度は、テーマを「常任委員会における議員間討論の活性化について」とし、講師に、平成11年に、全国最年少となる27歳で徳島県川島町長に当選され、町長を2期努められた後、地方自治の探求を目的に早稲田大学大学院に入学し、首席で修了され、現在、早稲田大学マニフェスト研究所事務局長として、自治体の行政・議会双方の支援を精力的に行われている「中村 健 さん」をお招きしました。
研修会では、混同しがちな「議論」・「討論」・「討議」の定義から丁寧にお話しいただき、議員間では、主張の正当性を争ったり、説得するのではなく、率直な意見交換をすることで、共通理解を探し出す「討議」が重要であることの説明を受けました。議員からは、自己主張に終始するのではなく、広い視野で意見交換をすることが、結果として、相互理解による共通の着地点を見出し、大きな成果につながる可能性が理解できた等の感想がありました。
令和6年3月25日(月曜日)
◆庄原市議会ガイドブックが完成しました!庄原市議会では、「投票率の低下」や「無投票当選の増加」等、全国的に地方議会が抱える様々な課題に対応するため、令和5年度から「広報広聴活動の充実化」を目標に掲げ、市民の皆さまに市議会の活動を知っていただくための様々な取り組みを検討しています。
その中で、将来の庄原市を担う子ども達に市議会に対する理解を深めてもらうことが非常に重要であると考え、議会運営委員会を中心に、市議会について分かりやすく理解するためのツールの一つとして「庄原市議会ガイドブック」の作成に取り組みました。
主には、市内の中学生・高校生を対象と考えて作成したものですが、日ごろなかなか触れることのない市議会の概要をまとめていますので、是非ご覧ください。
庄原市議会ガイドブック(改訂中)